パソコンやスマートフォン、タブレットなどのIoTデバイスの普及により、インターネットは身近な存在になりました。
そのことでテレワークという、自宅など会社から離れた場所でもインターネット経由で会社にいるのと同じように働く勤務形態が一般的にも普及し始めました。
テレワークは他にも、在宅勤務やリモートワークとも呼ばれ、語源や元々の意味合いは多少違っていたようですが、現在では同じ意味で使われていることが多いです。
しかし、少し前までテレワークを導入している日本の企業はごく少数で、IT関連の職種ですら通勤して働くのが一般的でした。
新型コロナウイルスの流行により広がったテレワーク
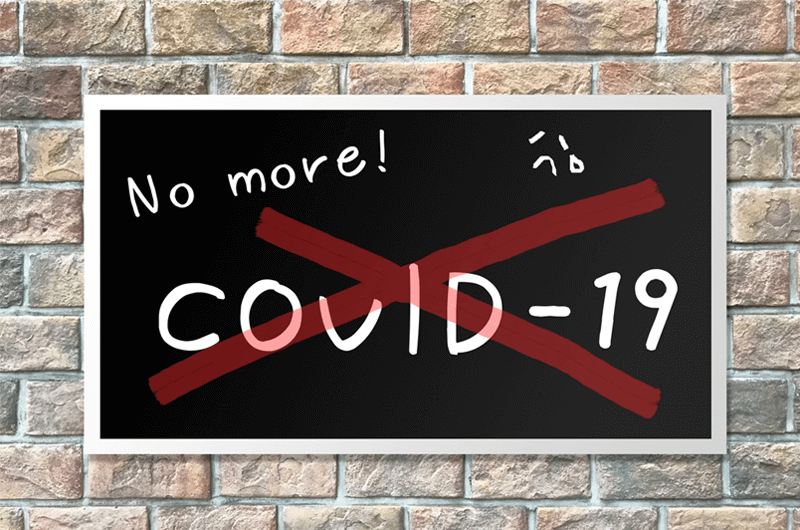
2020年の初め頃から話題になり始めた新型コロナウイルスは、当初は東アジア、特に中国で猛威を振るっていましたが、2020年6月現在では世界中に広まり、感染者と死者の多くが欧米に集中しているなど感染の中心地は東アジアから欧米に移りました。
新型コロナウイルスの流行により、世界中でロックダウンされる都市が相次ぎWHOはパンデミックを宣言しました。
コロナ禍以前の欧米諸国ではマスクをする習慣がなく、またマスクの効果自体が疑問視されていたため、日常的にマスクをしている人が少なくないアジア人を奇異の目で見る人が少なくありませんでした。
しかし、欧米と比べてアジアでは感染者および死者が比較的少ない傾向にあることから、現在では欧米諸国でもマスクの着用が当たり前になり、国や地域によっては公共の場でのマスクの着用を義務化させるなど価値観を一変させています。
一方で、感染被害のピークを過ぎたと見られる国が多い欧州に対し、南米ではブラジルを中心に感染者と死者が急増しており、WHOは南米が新たな中心地になる見解を示しています。
テレワークを導入するメリット
日本では、コロナウイルス感染拡大の第二波が予測されており、政府の発表する新しい生活様式ではテレワークやコアタイムの出勤を避ける時差出勤が推奨されています。
コロナ禍の現在、世界では『密閉』、『密集』、『密接』の三密を守るのが常識とされています。
しかし、満員電車は三密の最たる例であるものの、緊急事態宣言が出されるまでは満員電車で通勤せざるを得ない人も少なくありませんでした。
この三密を防ぐためにテレワークの導入が推奨され、テレワークに切り替える企業が増えています。テレワークには、働き手と企業側の両方の視点から見て以下のようなメリットがあります。
- 通勤が不要なため、三密を回避するだけでなく時間に余裕ができる
- インターネットにつながる環境であれば、どこでも働くことができる
- 赤ちゃんがいる方や体が不自由な方など、自宅でないと働けない方も働くことができる
- 気楽な服装で働くことができる
- 家族とのコミュニケーションが増える
- 災害時のリスクを分散・軽減することができる
- 寿退職など、離職率を減らすことができる
- 労働生産性が高まる
日本では都市部、特に首都圏は平均通勤時間が長い傾向にあります。これは、郊外や東京周辺県など家賃相場が比較的安い地域に住む人が東京都心部まで通勤している場合が多いことが理由と考えられます。
また、首都圏のラッシュ時の電車は非常に混雑しているため、三密を防ぐうえでテレワークは欠かせません。長くて混雑した通勤が無くなることで肉体的・精神的余裕が生まれ、労働生産性も高まり家族と接する時間も増えることでコミュニケーションが増えるなど、家庭環境にも良い影響が見込まれます。
テレワークを導入するデメリット
逆に、テレワークを導入する上でデメリットはあるのかと言われると、無いとは言えません。
メリットと比べるとデメリットは少ないと思われますが、以下のようなデメリットが考えられます。
- 在宅勤務だと一日中家にいる場合も多くなり、運動不足になりやすい
- 家庭環境によっては自宅で働くのが難しい場合がある
- 勤怠管理やコミュニケーションをとるのが難しい
- テレワークの導入自体が難しい職種が少なくない
- セキュリティ対策が煩雑になりやすい
2020年6月現在もコロナ禍は終息していないため、外出時には三密を避けることを忘れず運動不足解消のため通勤をしていた時間帯やお昼休みに散歩をするなど、なるべく陽の光を浴びられる時間帯に外に出ることをお勧めします。
自宅に自分の部屋が無いなど、家族がすぐ側にいる状態で働かざるを得ない人もいるかと思います。レンタルスペースを借りるなど、自宅外で働く方法もありますが、テレワーク中は自宅外で仕事をすることを禁止している企業や部署も存在します。社員の事情も考え、例外を認める形をとることも重要だと思われます。また、先ほどのメリットとは矛盾しますが、逆に家族といる時間が増えることで関係が悪くなる場合もあり得ます。
テレワークでは周りに同僚や部下、上司がいない状態で働くことになるため、勤怠管理やコミュニケーションをとるのが出社している時より難しくなります。そのため、勤怠に関するルール作りやコミュニケーションツールの準備が必要となります。
テレワークには導入自体が難しい職種も少なくありません。こちらについては後述で説明したいと思います。
セキュリティ対策についても詳細は後述で説明したいと思いますが、社外で作業を行うため情報漏洩のリスクが社内にいる時より高まります。
テレワークの普及率が低い日本の企業
日本ではテレワークの導入が他国と比べて進んでいるとは言い難く、パーソル総合研究所が4月10~12日に調査した結果では、テレワーク実施率の全国平均は27.9%で3月9~15日の調査結果(13.2%)から約2倍に増えてはいるものの、導入できていない企業の方が多いことが分かります。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴って、政府が7都府県に緊急事態宣言を発令した4月7日以降、社会人の働き方はどう変わったのか。パーソル総合研究所が4月10〜12日に調査した結果、テレワーク実施率の全国平均は27.9%で、3月9〜5日の調査結果(13.2%)から約2倍に増えた。政府は4月16日に対象地域を全国に拡大したため、テレワーク導入はさらに進みそうだ。
引用:ITmedia NEWS
日本の企業は、新しい技術を開発することは得意でも導入するのは遅い傾向があり、海外では大分前から時代遅れと言われているFAXが、日本では未だに広く使われていることからも読み取れます。新しいものを積極的に取り入れる柔軟さが日本企業の課題かもしれません。
ハンコは今の時代に合わない?
テレワークの導入が進まない理由の1つとして、日本のハンコ文化が関係しています。
日本では契約を行う上でハンコが必要になる場面が多いですが、テレワークに切り替えた企業や部署でもハンコを押すためだけに社員が出社する場合もあります。
そうなると、テレワークを行うメリットがあまりないため、導入はできるのに実施しない企業も出てきます。ただし、そのような状況を打破するためにハンコが不要な電子契約などが登場しており、今後普及が見込まれます。
また、日本在住の外国人は東日本大震災直後を除けば年々増加しており、ハンコにするのが難しい名前を持った人も少なくありません。
日本の労働生産性は先進国の中では最低レベルと言われており、これにはハンコ文化も関係している可能性があります。電子契約などの登場により、日本のハンコ文化は今後大きく変わることが予想されます。
そこで、これから普及が見込まれる電子契約やクラウドで利用可能な事務系のソフトをご紹介します。
クラウドサイン
クラウドサインは、電子契約の中でも国内シェアNo.1と言われており、これから電子契約の導入を検討されている企業様におすすめです。

クラウドサインを利用すると、このようなメリットが見込めます。
- ハンコだけではなく紙も不要になるので環境にも優しい
- 紙の申請書では発生していた郵送費や交通費、印紙税が無くなる
- 必須項目を自由に設定できるので記入漏れが無くなる
- 申請書の管理が容易になるため無駄な時間を削減できる
このように、ハンコを使った契約と比較した場合、費用面でも管理面でも非常に効率的になることが分かります。
一方で、クラウドサインに限った話ではありませんが電子契約におけるデメリットも存在します。
- 管理サーバーへのサイバー攻撃で、データの盗難や破壊、改ざんされる可能性がある
- 契約の種類によっては電子契約が認められていないものもある
- 電子契約を受け入れてない企業も存在する
ビットコインなどの仮想通貨でもサイバー攻撃を受けた例があるなど、データの流出や改ざんなどが100%無いとは言い切れません。
不動産関連の契約など、電子契約が認められていない種類の契約も存在します。ただし、これらの契約も電子契約の普及が進めば認められるようになるかもしれません。
電子契約は画期的なシステムですが、比較的新しいサービスで世間の認知度も高いとは言えないため、昔ながらのハンコを使った契約と比べて安心できないという企業は少なくありません。こちらも電子契約の普及が進むことで変わっていくと思われます。
会計freee
freee株式会社という、法人や個人事業主向けに事務管理を効率化するためのサービスを開発・運営する企業様が開発されたソフトです。
クラウドで利用できる会計ソフトで、パソコンにインストールを行う必要はないためWindowsやMacなどの機種を選ばないだけではなく、スマートフォンでも利用可能です。また、法人向けと個人向けがあり、30日間無料で試すことができます。
使える機能は料金プランによって異なりますが、必要最低限の目的で会計ソフトとして使用したい場合はミニマムやスターターで問題ないと思います。
こちらのソフトは簿記の知識が無くても使用でき、サポートが充実していて作業効率化を図る上で非常に有用です。一方で、月額または年額の課金制であるため、使い続けるにはお金がかかります。またソフト自体にすぐには慣れない場合も考えられます。
まずは無料で試して、その上で今後も使い続けるかどうかを判断されると良いかと思います。
人事労務freee
会計freeeと同じく、freee株式会社が開発した、クラウドで給与計算や勤怠管理、労務管理を行うことができるソフトになります。

法令改正や料率変更に自動で対応しており、また書類のやり取りが簡単になり、自動でバックアップを行うので安心です。
こちらのソフトもプランによって利用可能な機能が異なり、月額または年額の課金制であるため、無料お試し期間中に今後もお使いになるかどうかを判断されると良いかと思います。
システム運用に詳しい社員がいない
システムに詳しい社員がいない企業が多いことも普及が進んでいない理由にあげられます。独立行政法人 中小企業基盤整備機構によると、日本の企業の99.7%は中小企業であり社内に情報システム部などシステム関連の部署を抱えていない企業も少なくありません。
中小企業は、日本の全企業数のうち99.7%を占め、私たちの生活に密着した財やサービスの提供を行っています。また、中小企業の中には、世界市場の獲得につながる先端技術の活用や、地域で育まれた伝統と特性を有する多様な地域資源を活用する担い手となっている企業が多く存在します。
単にインターネット回線に接続できれば自宅でも仕事が完結できる業務なら問題ないかもしれませんが、実際にはVPN(Virtual Private Network)という、インターネット上に仮想的な専用線を設定してセキュリティ面で安全にデータ通信を行う必要がある場合も多いと思われます。
このVPNですが、セキュリティ面での安全性が高まる一方でデータを暗号化して通信しているため、通信速度が遅くなったり場合によっては接続自体ができなくなることもあります。そのためVPNに接続ができず、出社せざるを得ないという話も耳にします。
テレワークの導入が難しい職種
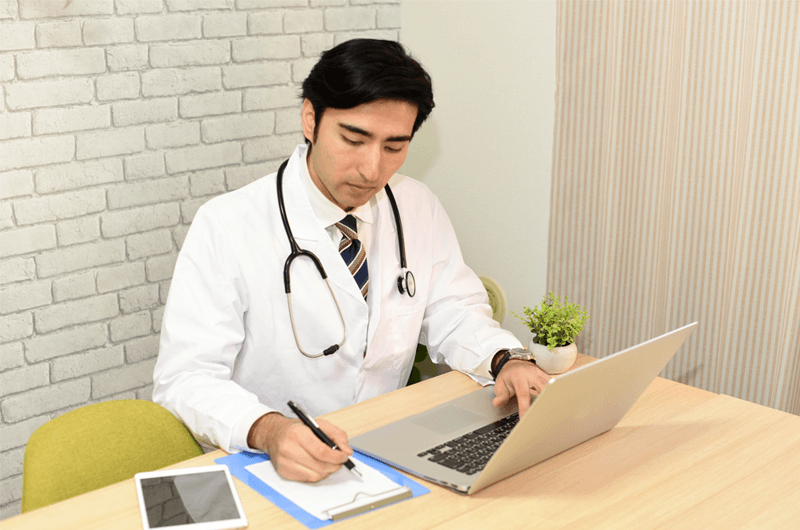
新型コロナウイルスの流行により普及し始めたテレワークですが、導入が難しい、もしくはできない職種も少なくありません。これらの分野の職種は、導入が難しいと思われます。
- 製造・生産関連の職種
- 接客・販売関連の職種
- 医療・福祉関連の職種
製造や生産関連の職種は、大型の機械や広大な土地が必要なものが多いため、自宅で行うことができません。また、作業工程によって担当者が異なる場合が多いため、1人で行うことは難しいです。
接客業の場合、一部ではテレワークで行われているものも存在しますが、直接お客様と会うのが一般的です。販売業も同様で、商品の受発注や商品登録などテレワークでも対応可能な作業もありますが、商品の補充や発送業務、店頭での販売などテレワークで行えない作業も多いです。
医療や福祉関連は、患者と直に接しなければならない職種で、テレワーク化が難しい職種の最たる例と言えます。世界では、医療従事者が新型コロナウイルスに感染して亡くなる例も多く見受けられます。
テレワークの導入が可能な職種
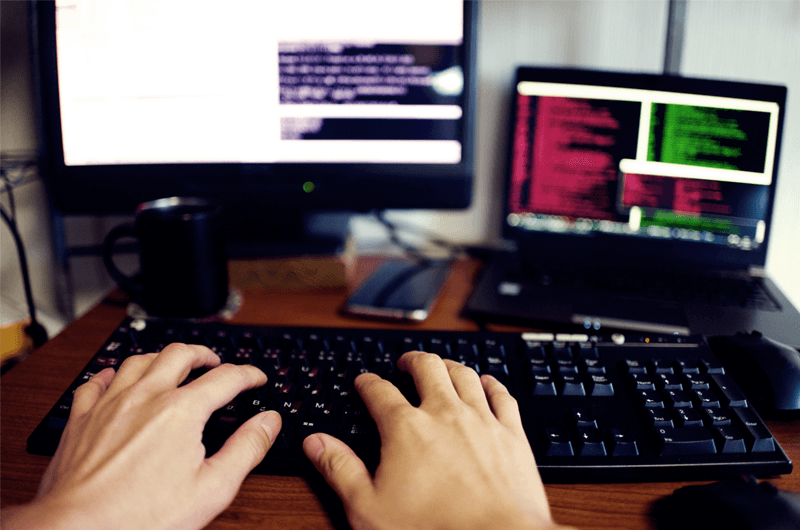
以下のような職種はテレワークが導入が可能と思われます。
- 事務職やプログラマーなどパソコンを主に用いる職種
- 教育関連の職種
- コールセンター関連の職種
- 営業関連の職種
事務職やプログラマーなどは、最もテレワークの導入がしやすい職種だと思われます。パソコンを使った業務が中心なため、ビジネスチャットツールなどを使えば他の社員との連絡も容易です。
学校や塾などの教育関係もオンラインで授業を行うなど、テレワーク化が可能です。ただし、勉強を教えるのが中心の塾とは異なり、学校はクラブ活動や学校行事など内容によってはテレワーク化が難しいものも多く、また体育など科目によってはオンラインでは満足に授業を行えないものもあります。
コールセンター関連の職種は、パソコンとネット環境、電話などがあれば導入は可能です。ただし、お客様からの様々な質問に答える必要があるため、経験の浅い人だと1人で全てを対応できない場合も多いです。そのため、個人情報など扱っている内容やオペレーターのスキルによっては導入が難しい場合もあるかと思われます。
営業関連の職種は普段から会社にいる時間は短めで外回りをしている時間が長く、日報や業務報告書の作成など社内で行う業務はテレワークで完結させることが可能です。
テレワークの導入で生み出された新サービス
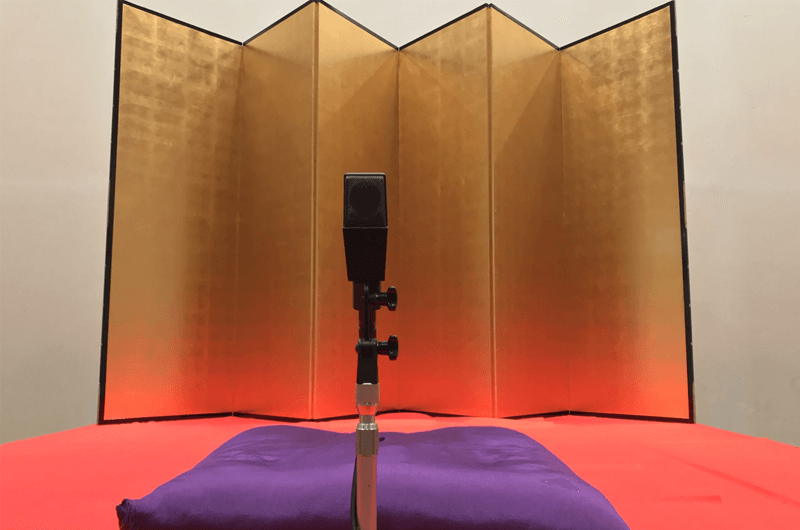
コロナ禍の影響で普及し始めたテレワークですが、そこから新サービスも誕生しています。
芸能界もテレワークの導入が始まっており、コメンテーターがオンラインで討論に参加している場面も見られます。
しかし、映画やドラマ、バラエティ番組のVTRなどはコロナ禍で新しく撮影するのが難しくなっており、放送中止や再放送で対応している場合も多いのが現状ですが、逆にコロナ禍を逆手に取ってテレワークのみで撮影および編集されたドラマやバラエティ番組も出てきています。
コロナ禍で公演の機会を失った芸能関係者は少なくありませんが、落語家がZoomを使って有料で落語を配信するなど様々な方法が取り入れられ、伝統芸能の世界にも変化が見られます。
新型コロナウイルスの感染拡大で公演を失った芸人たちが、動画配信に活路を見いだしている。無料視聴が一般的なYouTube(ユーチューブ)だけでなく、オンライン会議システムのZoom(ズーム)を使った有料配信の寄席が登場。「配信映え」に挑戦する若手芸人も現れた。
引用:朝日新聞
まだまだ一般的とは言い難いですが、オンライン結婚式というものも存在します。通常、結婚式と言えば大勢の家族や親類、友人が集まって行われるものというイメージですが、コロナ禍での三密を防ぐだけではなく、近年は国際結婚も珍しくなくなりつつあり外国にいる家族や親類、友人も高い渡航費を払わずに結婚式に参加できるというメリットもあります。
テレワークが行えないと思われている職種でも、工夫次第では可能なものもありそうです。
日本の企業がテレワークを普及させるのに必要な課題
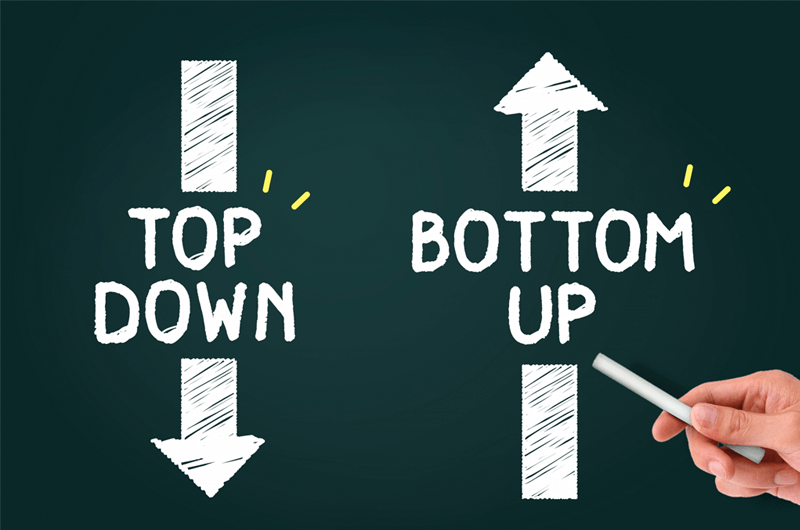
日本の企業はトップダウンと呼ばれる組織の上層部が下部組織に指示をする管理方式が多いですが、人間は年齢が上がるほど変化への対応力が下がる傾向にあり、上層部には定年以上の年齢になっている方が多く存在する企業も少なくありません。
そのため、企業の方針に必ずしも社員の意見が反映されているとは限りません。
根性論など古い価値観を見直す
昔の日本の企業では、結果を出す以上に遅くまで残業をするなど長時間働くことを評価する風潮もあったようです。
かつては「24時間、戦えますか。」というフレーズが出てくるCMがテレビで放送されていたなど、長時間労働を肯定をする風潮があり、年配の人にはこのような価値観で働いていた人も少なくないため、通勤が不要で自宅からリモートで働くことができるテレワークに対してサボっているなど楽をしていると捉える人も存在するようです。
前述でも触れましたが、日本の労働生産性が先進国で最低水準なのは、こういった根性論が重視されたことで生産効率よりも長時間働くことが評価されてきたことも原因の1つだと考えられます。
テレワークの導入には、価値観の変化も必要と言えます。
日本国内のネット環境を改善させ上手く活用する
日本はインターネット回線の普及率は高いのですが、外国人観光客からは日本では無料Wi-Fiが使える場所が少ないという話が出てくることも多く、また使える場所でも他国と比較すると利用率が高くはないなど、国民のインターネットに関する知識が決して高くはないという側面があります。
日本では高齢者のガラケーの使用率が高くなっていますが、スマートフォンの月々の使用料金がガラケーと比べて高いのも理由と考えられます。もちろん、ガラケーの方が使い慣れていたりスマートフォンの操作が苦手という理由で使われている方も多いと思いますが、インターネット関連の使用料金が他国と比べて高くなりがちなのは大きな課題と言えます。
実際にテレワークを導入する方法

いつ終わるかもわからないコロナ禍ですが、国内外で緊急事態宣言やロックダウンが解除される自治体が増えています。しかし、世界では規制を緩めてからクラスターが大量発生した国もあるなど、依然として気を抜けない状態が続いています。
東京オリンピックは来年の2021年に延期されましたが、現実問題として来年ですら開催が可能かどうかは不明な状況で、来年も開催できなければ中止になるという話もあります。
そのため、まだテレワークを導入していないという企業様には今からでも導入することをおすすめします。では、どのようにして導入すればいいかを紹介させていただきます。
ITツールを活用する
世の中には多種多様なITツールが有料・無料を問わず存在します。ツールによって行えることは様々ですが、テレワークを行う上で最低限これらの機能を備えたツールは用意しておきたいところです。
- 社員同士のコミュニケーションが取れるツール
- 社内の情報が共有できるツール
- Web会議が行えるツール
一部ではありますが、これらの機能を備えたツールを紹介させていただきます。
Chatwork
Chatwork株式会社が提供するクラウド型のビジネスチャットツールです。
主な機能として、特定のメンバーだけを対象にしたチャットルームを作成したり、個人間でのチャットを行うことができます。また、データの送受信を行ったり、過去のチャットのやり取り内容を検索することも可能です。
画面右側にはチャットルームの概要を書き記す箇所があり、またチャットルームに参加しているメンバーにタスクを登録をすることもできます。1対1であればWeb会議を行うこともできるため、テレワークを行わない場合でもChatworkを使用している企業は多いと思われます。

Garoon
サイボウズ株式会社という主にグループウェアの開発・販売・運営を行っている企業が提供するツールになります。
主に300人以上の規模がある組織を対象としたツールで、スケジュールの登録や社内情報の共有、社員情報の登録および確認、掲示板を使った意見交換など様々なことが可能です。

Zoomミーティング
前述でも触れましたが、アメリカに本社を置くZoomビデオコミュニケーションズが提供するWeb会議ツールで、Zoomと呼ばれることが多いです。
Chatworkは1対1のWeb会議には使えますが、複数人のWeb会議を行う場合はこちらが最適です。

プロにテレワークの導入支援を依頼する
餅は餅屋ということわざがあるように、やはりその道のプロに任せるのが一番確実です。
日本PCサービス株式会社では、ドクター・ホームネットという主に個人向けのパソコン修理を行う事業を行っていますが、法人向けにテレワークの導入を支援するサービスも行っているようです。
IT機器の設定・トラブル解決を行う日本PCサービス株式会社(本社:大阪府吹田市、代表取締役社長:家喜 信行、証券コード:6025、以下「当社」)は、新型コロナウイルスの流行を受け、2020年3月9日(月)より在宅勤務を推奨する法人向けに、IT機器レンタルサービス「在宅勤務まるごと支援プラン」の受付を開始いたします。
引用:日本PCサービス株式会社
業務用ルーターへの切替で最短3日で在宅勤務を可能に!!【従業員数20名以下の中小企業対象 : 初回100社まで】
オフィスのデスクトップパソコンを家に送って、そのまま使える!
引用:日本PCサービス株式会社
IT機器の設定・トラブル解決を行う日本PCサービス株式会社(本社:大阪府吹田市、代表取締役社長:家喜 信行、証券コード:6025、以下「当社」)は、ハートコア株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:神野 純孝)と業務提携し、在宅勤務時の従業員の業務を可視化する「HeartCore TaskMining」(以下「タスクマイニング」)の提供・導入時の設定サポートを2020年4月20日(月)より開始します。尚、タスクマイニングは2020年7月末まで無料提供となります。
引用:日本PCサービス株式会社
VPNの設定などテレワークの導入支援を行う業者は他にもありますが、設定後のトラブルサポートには対応していない場合もあります。
設定済みのパソコンのレンタルやVPNの設定、HeartCore TaskMiningといった社員の作業管理ができるツールの導入など、導入支援の内容も様々です。
テレワークを導入する企業が増えたことで、今後はコロナ禍が終息してもテレワークを継続する企業や労働者が増えることが予想されます。また、テレワークの導入をきっかけにオフィスの賃貸契約を解除したりオフィス面積を縮小する企業も増えており、経費削減効果も見込めます。
求人情報にテレワーク可といった内容を盛り込めば、今までは勤務地を見て応募を見送っていた層からも応募が来る可能性が高まるなど優秀な人材が獲得しやすくなり、雇用を拡大して会社を成長させていく上でも大きなメリットがあります。
日本PCサービス株式会社に依頼してテレワークを導入し、多様な働き方が可能な職場環境を目指しましょう。
前述でも触れましたが、日本PCサービス株式会社はドクター・ホームネットという主に個人を対象としたパソコンの修理や設定を行うサービスも運営しており、Wi-Fiの速度が遅い、壊れたパソコンからデータを救出したいなどパソコンの事でお困りでしたらこちらのご利用もおすすめです。


